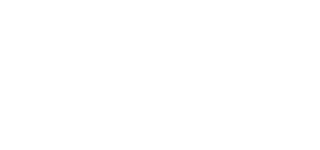- ホーム
- 考えよう、ごみのこと
- 考えよう、ごみのこと
- 「定禅寺通、資源とビジネスのゆくえ ~グローバルの動向、ストリートの実践~」イベントレポート(後編)
考えよう、ごみのこと
「定禅寺通、資源とビジネスのゆくえ ~グローバルの動向、ストリートの実践~」イベントレポート(後編)
2024年12月7日(土)、定禅寺通沿いにスペースを構える交流拠点『IDOBA』を会場に、ごみの減量化や再資源化について考えるイベント「定禅寺通、資源とビジネスのゆくえ ~グローバルの動向、ストリートの実践~」が行われました。
後編では、定禅寺通エリアで実施された2つのプロジェクトの紹介を中心に、参加者との質疑応答も行われた「コミュニケーショントーク」の様子をお伝えします。
第一部を終えた会場では、軽食とドリンクの提供がありました。この日提供された軽食は、仙台市の定禅寺通等食品リサイクル推進モデル事業に参画する店舗から調達されました。この取り組みは、市内店舗で排出される食品廃棄物のバイオマス資源化に貢献するもので、食事と共に紹介されました。
また使用する箸は再生ポリスチレン製で、後のコミュニケーショントークで紹介される「プラレターポスト」に“投函”すれば、ケミカルリサイクルの原料になるものが使用されました。
休憩後の第二部では、都市デザインワークスの榊原 進さんを進行役に、2つのプロジェクトに関わった4名の登壇者からお話をいただきました。
第二部 コミュニケーショントーク 儲かる?サーキュラープロジェクトの挑戦
モデレーター:特定非営利活動法人 都市デザインワークス 代表理事 榊原 進氏
事例提供①
「JOZENJI STREET Circular Project」
一般社団法人定禅寺通エリアマネジメント 大井 菜摘氏
アサヒユウアス株式会社 古原 徹氏
榊原
第一部のミニレクチャーとキーノートトークのお話から、ものづくりだけでなくサービスも含めたアライアンスから、どう資源の循環を作っていけるかという課題があがりました。そのヒントが、定禅寺通で行われたプロジェクトにあるのではないかと考えています。まずは、定禅寺通のケヤキの剪定枝と、仙台市の各家庭から収集したプラスチック資源を混合して「JSCタンブラー」を制作し「JOZENJI STREET Circular Project」についてお話をいただきます。
大井
定禅寺通でまちづくりに関わる活動をしています、定禅寺通エリアマネジメント(JSAM)の大井と申します。仙台市は、2023年に環境省が実施する「脱炭素先行地域」に選定され、定禅寺通を含む3つのエリアで脱炭素化の取り組みが進められています。「JSCタンブラー」はその一環として生まれました。
定禅寺通のアイデンティティであるケヤキの木ですが、毎年剪定された枝は活用されずに焼却処分されていました。そこで剪定枝を使ったサステナブルな取り組みを検討していた時に、並行して仙台市が家庭から出るプラスチック資源を製品化する段取りが進められていたので、この2つを使って定禅寺通のブランディングにつながるプロダクトを作ることになりました。全体の統括はJSAM、原料提供は仙台市、そしてサステナブル商品の開発・製造に携わるアサヒユウアスと3者による協働によって「JSCタンブラー」が誕生しました。
古原
アサヒユウアスは、アサヒグループジャパン直下のベンチャーとして、循環型社会を形成するための新しい取り組みを行っています。今回開発に関わったタンブラーは家庭から集められたプラスチック資源を原料に使うのですが、どんな状態のものが入っているか分からない状態でした。そのまま使うことにはちょっとリスクがあるということで、表面は食品対応の新しいプラスチックでコーティングしました。すごく薄いので、使用量としては微々たるものですが、実はこのコーティングが大変でした。漆器の職人さんに手塗りをしてもらっているんですけれど、プラスチック資源に残っていた紙片やアルミがちょっと混ざっていて、それが表面に出ているとそこからコーティングがはがれてしまう。でも長年の技術をもった職人さんが塗る前に色々な工夫をしてくれて、ちゃんと食器として使えるようになりました。
大井
このタンブラーには2つの全国初があります。1つは、プラスチック資源の再商品化、もう1つはケヤキとプラスチック資源を混合した材料の再商品化です。
またタンブラーは1個2,000円で販売していますが、そのうち100円はまちづくりに還元されるかたちを取っています。販売はイベントなどで随時行っていますが、市民の皆さんがこのタンブラーを目にする機会をもっと増やしていきたいと考えています。
榊原
ありがとうございました。皆さんからのご質問はありますか?
参加者
アライアンスを組むうえでなかなか結びつきづらい3者が組んでいると感じますが、どういったプロセスでマッチングがなされましたか?
大井
JSAMではケヤキを何とかしたい、行政としてはプラスチック資源を何とかしたいということで話を進めるうちに、丸紅の松浦さんのご紹介で古原さんを紹介していただきました。
前提的な話になりますが、定禅寺通のケヤキに対する皆さんの思いは相当なものがあると常々感じています。“ケヤキラブ”がすごくて(笑)、何とかしていきたいという思いで皆さんが同じ方向を向けたことで、取り組みがスムーズに進んだと感じています。
参加者
販路の拡大など、今後の展開はありますか?
大井
販売はイベントなど部分的に行っていたのですが、今後はWebでの展開や、企業様にお求めになっていただくかたちを模索しています。あとは定禅寺通周辺でのイベントのグッズとコラボしたり、あとはこのタンブラーで飲むドリンクの開発を進めたりしています。
古原
海外のクラフトビールで多いんですけど、香りが出る木をビールに漬け込んで、香りをビールに移す製法があるんです。それで今回、剪定されたケヤキの木を熱して香りを出してシンプルなビールに漬け込む試験醸造をしてみたら、結構美味しいものができました。このクラフトビールを販売していく相談を始めているので、完成の暁にはぜひ飲んでください!
事例提供② 「Plaletter~PSケミカルリサイクルで実現!プラごみゼロイベント~」
東洋スチレン株式会社 齊藤 岳史氏
東商化学株式会社 岩辺 元氏
榊原
次のプレゼンテーションは、この赤いボックス「プラレターポスト」に関する内容です。ポリスチレンの完全循環に貢献する取り組み「Plaletter~PSケミカルリサイクルで実現!プラごみゼロイベント~」についてご紹介をお願いします。
齊藤
東洋スチレンの齊藤と申します。東洋スチレンは、デンカをはじめとする3社が事業統合して設立されたポリスチレンを製造するメーカーで、千葉県市原市で稼働するケミカルリサイクルプラントの運営も担っています。
ポリスチレンのケミカルリサイクルの取り組みのなかで、私どもが掲げたのが、ポリスチレンの回収ボックスである「プラレターポスト」を用いた回収循環のコンセプトです。
ポリスチレンの完全循環にあたり、重要なことが3つあります。プラスチックの種類をポリスチレンに統一する「分別」、ポリスチレンの使用現場で回収・減容して分別と輸送エネルギーを削減する「輸送」、そしてケミカルリサイクルで新品同等の再生ポリスチレンを作る「品質」です。このポイントを実現させてサイクルを回すことで、ポリスチレンの完全循環が成り立ちます。
この仕組みを実際に使って、仙台市で開催された2つのイベントで実証しました。最初の取り組みは、2024年9月27日・28日に行われた定禅寺通エリアのゼロカーボンPRイベント「JOZENJI STREET Zero-carbon Challenge」(「SENDAI SDG’s Week 2024」)です。来場者が飲食の際に使用したポリスチレン容器を、会場内に設置した「プラレターポスト」に入れていただいて回収し、小型の減容機を用いてその場で減容を行いました。さらに11月に仙台市内で行われた「第16回エコバランス国際会議」では、再生ポリスチレンで作ったカトラリーを来場者の方に使用していただき、使用後はまた「プラレターポスト」に入れてもらって回収する、という初めての試みを行いました。その時のカトラリーを作っていただいたのが、東商化学様です。
岩辺
我々は使い捨てのカトラリーをメインで製造しているメーカーでして、大量生産・大量消費の時代とともに成長してきました。しかしながらこれからは、使い終わったものがリサイクルによって再び使えるものになる、そうした取り組みを東洋スチレン様と一緒に展開していきたいと考えています。
日本では2022年にプラスチック資源循環促進法が施行され、使い捨てのカトラリーを含む特定プラスチック使用製品を対象に、事業者に対してプラスチックごみの削減に取り組むことが求められました。
しかし使い捨てのカトラリーをリサイクルする際には課題がありまして、先ほど古原さんがおっしゃったように、マテリアルリサイクルの原料となるプラスチック資源には何が混ざっているのか分かりません。食品衛生法に基づくと、そうした原料は使用できないことになります。ですからカトラリーを再生するにはケミカルリサイクルが必須になります。この技術が確立されることによって、これまでリサイクルに回したくでもできなかったものも再生される可能性が広がるのではないかと期待しています。
榊原
ありがとうございました。質問はありますか?
松八重
東洋スチレン様、東商化学様には「第16回エコバランス国際会議」の際にポリスチレン容器のリサイクルで大変お世話になりました。海外ではポリスチレンというと嫌われ者扱いで、会議でポリスチレン容器を使用することに対してかなり懸念をもたれていました。でも私は、他の国ではできない仕組みだからむしろやろう、と。結果、海外から来た方からもポジティブな意見をいただくことが多かったです。
榊原
素朴な疑問ですが、なぜ海外ではポリスチレンが嫌われるのでしょうか?なぜ他の国ではできない仕組みなのでしょうか?
松八重
感覚的に、ポリスチレンがワンウェイ(使い捨て)の代名詞のような印象を持たれていて、使ってすぐに捨てるというところに良い印象を持っていないようです。それと「分別して回収する」仕組みは日本ならではです。海外では量を確保しますけれど、分けるまでは進んでいない印象です。
齊藤
我々も現在は市原市の家庭から出る使用済ポリスチレンを資源として集めています。ポリスチレンと分かりやすいもの、たとえば乳酸菌飲料の容器や発泡スチロールなどはしっかり分別していただいています。リサイクルに協力しようという意欲、環境に対する意識が高いんだなと感じているところです。
榊原
市民の立場で見ると、日本はリサイクルに関する意識が進んでいるということでしょうか。
松八重
日本では「分別しましょう」という仕組みがあると比較的遵守されやすいです。一方でその循環した製品を積極的に買うかというと、そうしたことにアンテナを張っている人は海外の方が多いように感じます。
古原
日本でもエシカル消費に対する消費者動向調査は毎年行われていますが、「高くてもサステナブルな製品を買う」という意識が低い結果が出ています。B to Cに対して「良いことをして出来ている製品だから高くても買ってよ」ということは難しくて、それ以外の価値を付けていかなくてはいけないと思います。
岩辺
我々はB to Bへの発信ですが、今までの製品は1回使ったら捨てられて焼却されていたので、できるだけプラスチックの使用量を減らして簡素な形状とするのが当たり前でした。けれどこれから製品をリサイクルしていく時には、デザイン性や機能面を追求したものにしていきたいと考えています。循環していくからこそ付加価値を与える、そういう意識を発信していける設計を心掛けていきたいと思います。
榊原
ありがとうございました。まだまだ話は尽きませんが、話を聞いていて、B to C、企業と一般消費者とのビジネスについての話がありましたが、さらにこれからの循環型社会の実現においては、B to Cは「Brand to Citizen」、資源循環によって生まれたブランドを消費者としてのコンシューマー(Consumer)だけでなく市民(Citizen)と共にどう作っていくのか、という視点が必要だと感じました。
クロージング・参加者からの感想
参加者からの活発な意見や質問が絶えないなか、コミュニケーショントークは終了。イベントは盛況のうちに幕を閉じました。イベント終了後、参加者の方に感想を聞いてみました。
リサイクルの情報収集のために参加したという方は、「ケミカル素材のことを積極的には知らなかったので、取り組みの実情を知れてとても参考になりました。また分別や回収など、資源を循環させるために課題になっている視点は、素材が違っても共通している点があると感じました」と話していました。
また環境分野を学んでいるという学生の方は「企業や行政がごみ削減やリサイクルをどう実践しているのか、学生の立場だと実際の活動にあまり触れる機会がありませんでした。だから今日は実際に活動している人たちから実践的なお話が聞けて、非常に貴重な機会になりました」と話してくれました。
イベントが終了した後も、会場では時間の許すかぎり登壇者と参加者、また参加者同士で意見を述べ交流を深める姿が見られました。このイベントをきっかけに定禅寺通から新しいアライアンスが生まれ、資源循環を促進するビジネスや市民活動が創り出されるかもしれません。